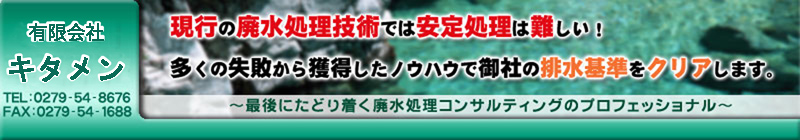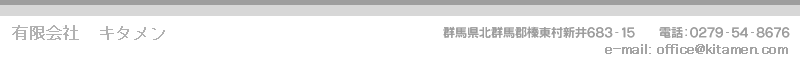|
|
|
 |
A.�Х륭�Ǥ�������ݤ��ФƤ��ʤ����Ǵ���Х륭������ݤ��ФƤ���л�����Х륭������ξ�Ԥ�ʻȯ�Х륭�Ǥ���
���к���磱������٤λ���������ư�ϡ��ˡ�����ǽ�Ϥγ�ǧ��
����磲���۵������ޤ��б������θ幱��Ū�к���»ܡ�
���۵�����ٷڸ����μ»ܡ������̤����䤹��������γ��̶��DZ�ťǻ�٤�夲�롣���θ屿ž��ˡ���ѹ�����
|
|
|
 |
A.̤�������ϲ�����Ǥ�����ȿ������֤Ǥ��Τ����դ��Ƥ���������
�������墪�����墪�������ή������pH����ʪ���������в���������ޤ��Ѳ���̵�����̤�����ȿ��ꤵ��ޤ������ޤ��pH���������Ƥˤʤ�ʤ���������ޤ��ΤǸ�������
�������פǤ��ʰ��ֳμ¤˲��ޤ��ˡ�
���к���磱���������ѻ���̤�����Ȳ������ʬ���롣
����磲��̤���������������á���ť���á���ٷڸ����μ»ܡ�
��������������̤餹���ַ�������
|
|
|
 |
A.ȯˢ�θ������礭��ʬ���ƣ����ʬ�ष�Ƥ��ޤ���
����ˢ��̤������ȯˢ
���к�����ť�������������Ƥ��ޤ�����ť�����䤷�Ƥ���������
���㿧��ˢ��Ǵ��ȯˢ
���к�����ť�����Ƕ��������Ƥ��ޤ��Τ����ä��Ʋ�������â�����٤�Ǵ���ξ���ȯˢ���������礬����ޤ��Τǡ��դ˶�����ʤ�����Ǵ�����ٹ礤�����Ŷ�����õ��ɬ�פ⤢�ꤨ�ޤ���
���㿧��ˢ��������ȯˢ
���к����������Ǵ�������Ƥ���Τ�����Ǥ����۵���Ǵ������ޤ�Ǵ��ʪ����������Ƥ��顢����ݶ���ޤ������ݤ��Ǥ��ޤ�������Ū�к��Ͻ���������ťǻ�٤�⤯�ݻ����ơ������ݤ˱��ܤ�Ϳ���ʤ��������פǤ���
�����ץݥ����
���������ݤ����й�����������ȸ��äƶ����̤餹�ȡ�Ǵ���ٹ礤�������ʤꡢǴ���Х륭������������ޤ���
���������ݤ���Ĺ®�٤��٤�����ȸ��äơ���ť�����ȴ����̤�������ν����㳲������������ޤ���
|
|
|
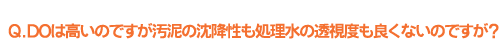 |
A.������ť�ϴĶ����ˤ�ä�Ǵ��ʪ��������դ��ޤ������λ���BOD����Ǥ��ݼ褷�ޤ����ä�DO�ͤϹ⤯�Фޤ�����BOD�λ������ʤޤ�̤�����ȤʤꡢǴ���Х륭��Ʃ���ٰ����θ����Ȥʤ�ޤ���
���к���DO�ͤ�̵�뤷���ե�Хå����Ʋ������������夫��������ˤ�����pH��0.3�ʾ夵��������
|
|
|
|
|
|